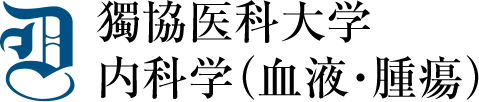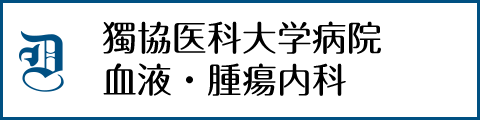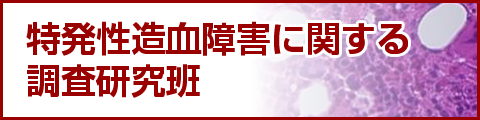診療案内
詳細は獨協医科大学病院 血液・腫瘍内科をご確認ください。
対象疾患
診療の対象疾患
当科の診療の対象は、
- 造血器腫瘍:急性・慢性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群など
- 各種の貧血:再生不良性貧血、赤芽球癆(ろう)、ビタミンB12欠乏性貧血など
- 各種の出血性疾患:血小板減少症、血友病を含む血液凝固異常症など
などの血液疾患全般です。
一般に、
- 血液検査で白血球数・血小板数などの増加や減少などが認められた
- 出血などによらない原因不明の貧血がある
- リンパ節の腫れが続き、リンパ腫が疑われた
- あざ(紫斑)ができやすい、歯肉出血や鼻出血が止まりにくい
- 原因不明の発熱が続いている
などが当科に受診される患者さんに認められる症状です。
当科では遺伝子診断を含む最先端の分子生物学の技術や、各種の分子標的薬や細胞療法を導入し、さらに造血幹細胞移植にも対応し、総合的に血液疾患の診断にあたっています。疾患の多くは治療に特殊な薬剤や無菌環境が要求されます。当科では無菌室11床・完全無菌室2床を含む43床の血液疾患専用病棟を備え、患者さんの診療にあたっています(日本血液学会専門医10名、造血細胞移植認定医5名)。
遺伝子診断などの分子生物学の技術を導入して、総合的に血液疾患の診断にあたっています。年間の入院数は2024年約360人です。
入院となる患者さんの疾患の内訳は悪性リンパ腫が約51%と最多であり、急性白血病が約24%、多発性骨髄腫が約10%、骨髄異形成症候群が約5%とこれに続きます。残りの約10%が再生不良性貧血や特発性血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)、感染症などの症例です。
当科において専門的に実施している治療:
- 悪性リンパ腫では外科系各診療科や病理部とも連携して疑われた時点から介入し、腫瘍組織の表面マーカー検査・染色体分析や遺伝子検査も必要に応じて行い、たくさんの病型を正確に診断することに努めています。さらにFDG-PET検査・骨髄検査などによって病期診断を行い、診断に基づいて化学療法や自家末梢血幹細胞移植を行っています。リツキシマブやオビヌツズマブ、ブレンツキシマブ・ベドチンなどの抗体医薬やイブルチニブ、ボルテゾミブ、レナリドミドなどの分子標的薬、ベンダムスチンなどの新規治療薬も組み合わせて治癒を含めた治療成績の向上に努めています。また、放射線科とも連携し、放射免疫療法の実施体制も整えています。また、二重特異性抗体療法やCAR-T療法なども導入しています。
- 急性白血病では標準的な化学療法に加え、対象となる症例ではチロシンキナーゼ阻害薬などの治療薬も使用して治療を行っています。高齢者や合併症のある方では、ベネトクラクス、アザシチジンなど分子標的薬を選択することもあります。適応となる症例では同種造血幹細胞移植を積極的に行っています。
- 慢性骨髄性白血病、骨髄増殖性腫瘍(真性多血症や本態性血小板血症など)の治療は主に外来にて行っています。慢性骨髄性白血病はチロシンキナーゼ阻害剤(イマチニブ、ダサチニブ、ニロチニブ、ボスチニブ、アシミニブ) の治療により90%以上の治療効果を得ています。骨髄増殖性腫瘍においてはアナグレリド、ルキソリチニブなどの新規薬剤も必要に応じて用いて治療を行います。
- 多発性骨髄腫については、症例ごとに自家末梢血幹細胞移植も含めた治療戦略を策定し、長期間の疾患のコントロールに努めています。ボルテゾミブ、レナリドミドのほか、ポマリドミド、カルフィルゾミブ、エロツヅマブ、ダラツムマブ、イサツキシマブなど、多彩な抗体医薬・分子標的薬を組み合わせた治療を行っています。また、放射線科とも連携し、放射免疫療法の実施体制も整えています。二重特異性抗体療法やCAR-T療法などの最新治療も導入しています。
診療の実績
外来患者数(2024年4月〜2025年3月)
新規患者数 362人/年
再来患者数 16,202人/年
入院患者数(2024年4月〜2024年3月)
入院患者数 362人
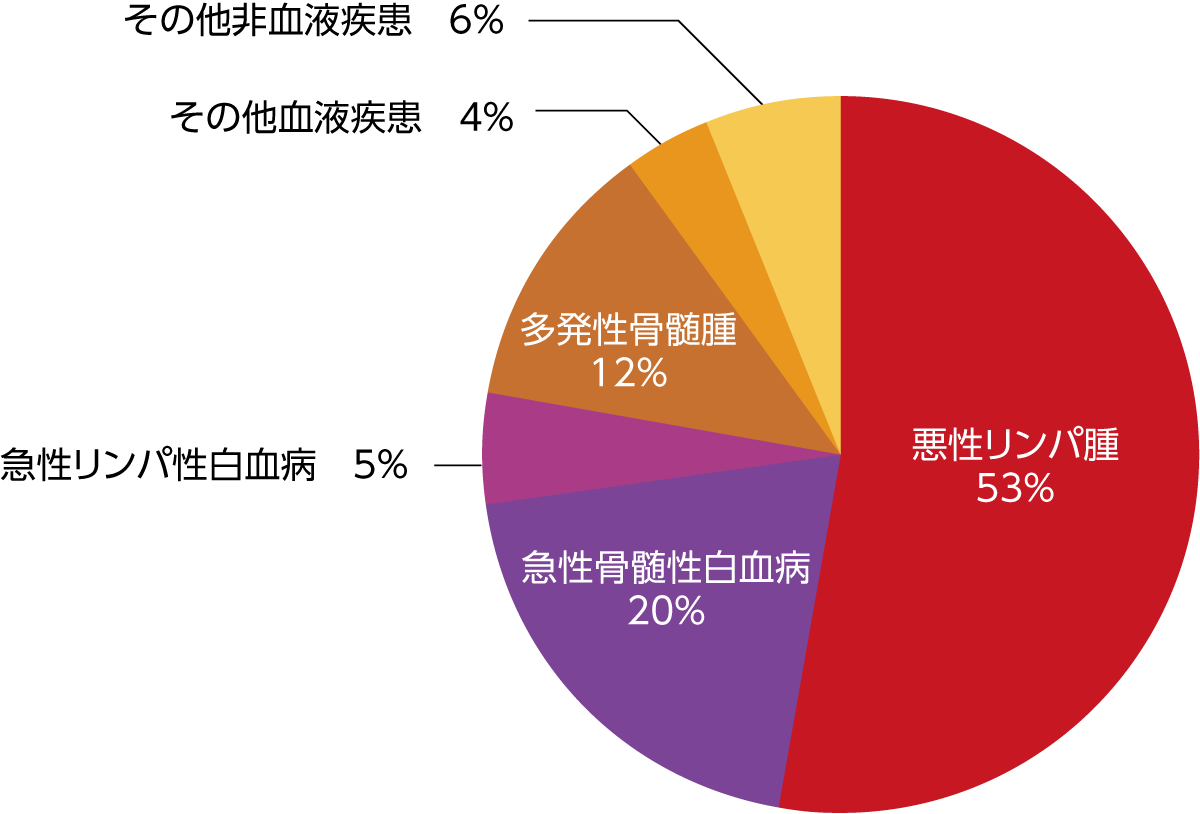
日本血液学会 血液疾患登録症例数(2024)
20124年1月1日から12月31日までに詳細な分類も含めて診断が確定した症例
| 総数 | 208例 |
| 内訳: | |
| 悪性リンパ腫 | 81例(慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫3例、マクログロブリン血症4例を含む) |
| 多発性骨髄腫 | 15例(髄外形質細胞腫含む) |
| その他の形質細胞異常 | 13例 |
| 骨髄異形成症候群 | 21例 |
| 急性骨髄性白血病 | 21例 |
| 急性リンパ性白血病 | 3例 |
| 慢性骨髄性白血病 | 2例 |
| 骨髄増殖性腫瘍 | 17例 |
| 特発性血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症) | 10例 |
| 再生不良性貧血 | 4例 |
| その他 | 21例(赤芽球癆、低ガンマグロブリン血症、寒冷凝集素症、ビタミンB12欠乏性貧血、後天性血友病など) |
移植の実績
当科は日本造血細胞移植学会の非血縁者間造血幹細胞採取施設、移植施設の両方に認定されおり、5名の造血細胞移植認定医が在籍しています。
同種造血幹細胞移植が適応となる患者さんに対しては、ドナーとして血縁・非血縁、幹細胞源として骨髄・末梢血幹細胞・臍帯血、前処置として骨髄破壊的・非破壊的前処置を患者さんの状態に応じて選択しています。また、近年はHLA半合致移植も行っております。悪性リンパ腫や多発性骨髄腫などの患者さんで適応となる場合は、自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法を施行しております。
2022年1月から2025年5月の間に、同種造血幹細胞移植は合計25例(血縁者間:骨髄0例、末梢血幹細胞2例、非血縁者間:骨髄7例、末梢血幹細胞5例、臍帯血:4例、HLA半合致7例)施行し、疾患の内訳は急性骨髄性白血病 12例、急性リンパ性白血病 4例、悪性リンパ腫 3例、再生不良性貧血 0例、骨髄異形成症候群 6例となっています。
また、同期間に自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法は合計17例施行し、疾患の内訳は悪性リンパ腫 4例、多発性骨髄腫 12例、骨髄異形成症候群 1例です。