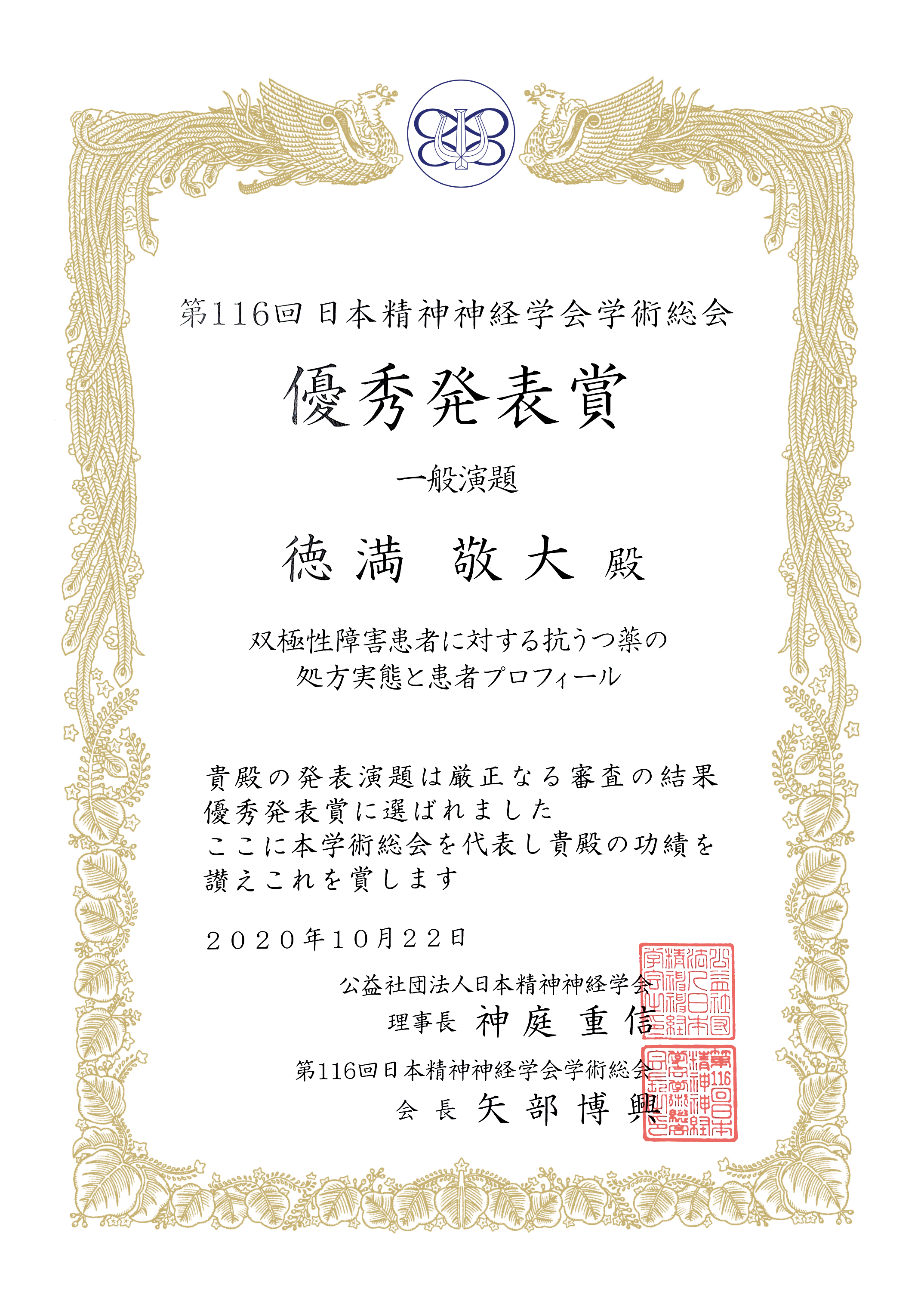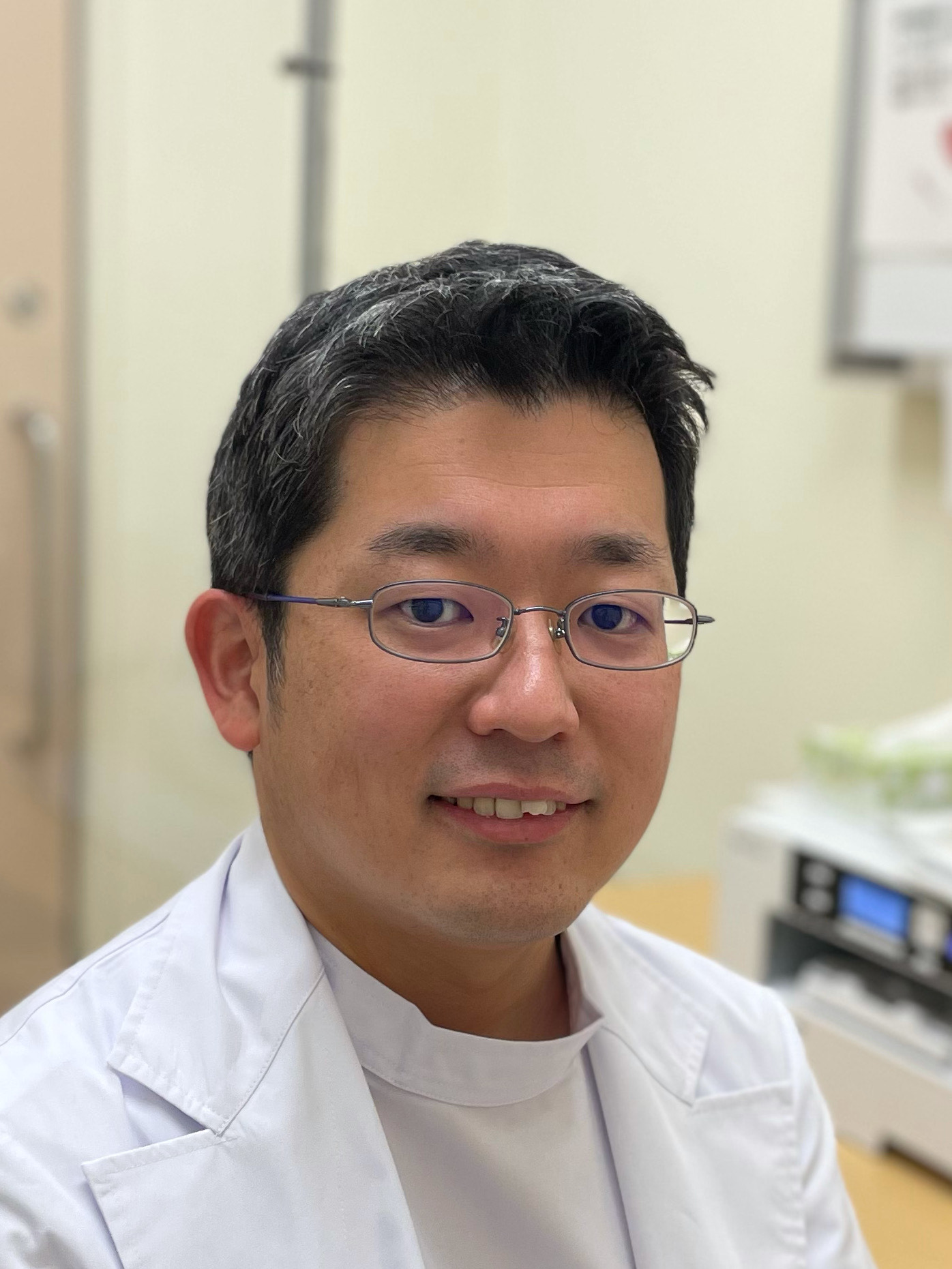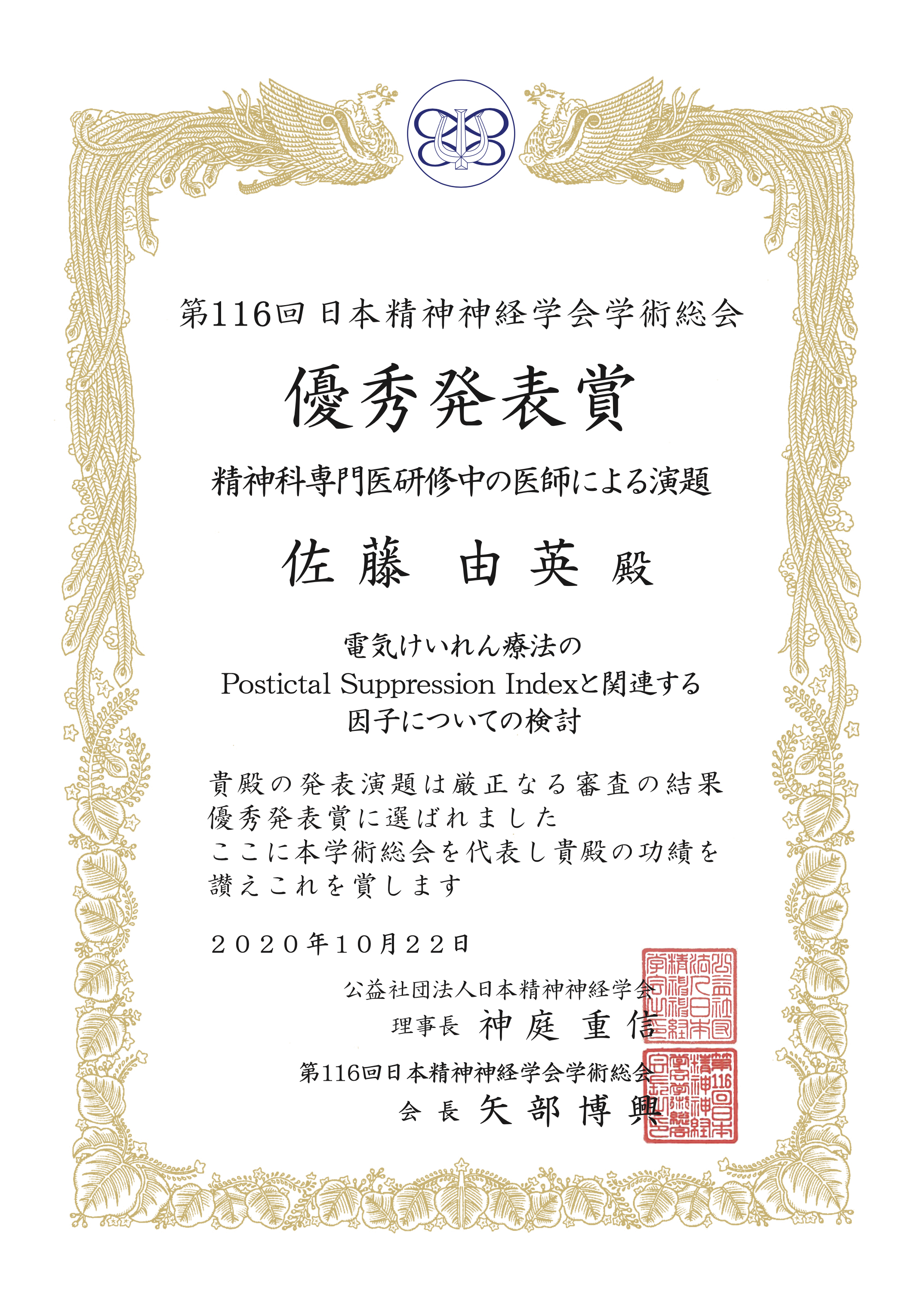第36回日本総合病院精神医学会総会優秀発表賞を受賞して
獨協医科大学精神神経医学講座 川俣安史
この度、「統合失調症患者への下剤開始と関連する因子の解析:20年間の後ろ向きコホート調査」と題して、第36回日本総合病院精神医学会総会で発表したところ、優秀発表賞に選ばれました。本研究は栃木県内の当講座関連病院および青森県内の病院を含む14施設で行われた多施設共同試験になります。ご協力頂いた関連病院の先生方に厚く御礼申し上げます。学会で表彰されるのは人生初の出来事であり、未だ夢うつつではありますが研究内容について簡単にご紹介させていただきます。
統合失調症患者同一症例の下剤および向精神薬を含む処方を20年間5年間隔で調査し、その結果は全症例(n=716)のうち25.1%の患者が2001年に下剤を処方され、2021年では34.1%が下剤を投与されていました。下剤の投与を受けている患者は経時的に有意に増加し、その中でも非刺激性下剤(酸化マグネシウム、ルビプロストン、エロビシキバット)の投与が有意に増加していました。下剤の開始と有意に関連した因子は女性、年齢、全ジアゼパム換算値、レボメプロマジン、オランザピン、ゾテピン、リチウム、カルバマゼピンの投与量でした。本結果から統合失調症薬物治療ガイドラインに準じてベンゾジアゼピン、リチウム、カルバマゼピンの使用を控えることが便秘の予防に重要と示唆されました。レボメプロマジン、オランザピン、ゾテピン投与中の患者に便秘の注意深いモニタリングが必要とも示唆されました。
ポスター作製にあたり、現在EGUIDEで研究指導を賜っている岐阜大学大井一高先生から教えていただいた「綺麗な図の作り方」を実践し、受賞に至ったと考えています。私は勝手に現在「WEB国内留学中」と称しておりますが、医局で働きながら学外の一流の先生方の研究指導を受けられることは当講座の大きな魅力です。これからも質の高い報告ができるよう研鑽を重ねてまいります。
日本臨床精神神経薬理学会 2023年ポール・ヤンセン賞を受賞して
獨協医科大学精神神経医学講座
医療法人藍生会 不動ヶ丘病院 岡安寛明
2023年3月に雑誌General Hospital Psychiatryに掲載された拙著論文『Effect of antipsychotic use by patients with schizophrenia on deceleration capacity and its relation to the corrected QT interval』が、この度、日本臨床精神神経薬理学会において2023年ポール・ヤンセン賞を受賞されました。名誉ある賞をいただきまして、本研究に関わっていただいた全ての方にこの場を借りてお礼申し上げるとともに、内容について簡単にご紹介いたします。
抗精神病薬による治療を受けている統合失調症患者は、心臓突然死のリスクが高いといわれております。心臓突然死の予測因子であるQT間隔は、抗精神病薬投与により延長するといわれていますが、一方で、QT間隔は不完全な指標ともいわれています。
心拍変動は、心拍の1拍ごとの変動であり、心臓の予備能や自律神経緊張の指標と注目されております。心拍変動の指標のうち、減速能(deceleration capacity : DC)の低下は、心臓死の強力な予測因子として知られていることから、抗精神病薬服薬中の統合失調症患者においてDCを測定し、抗精神病薬との関連、およびQT間隔との関連について評価しました。
抗精神病薬を内服している統合失調症患者138名に対してDCを計測し、得られた結果と患者の年齢、性別、体格指数、PANSS総スコア、QTc (Hodgesの補正式)、内服内容との関連を重回帰分析で検討し、さらに健常者からもDCを測定し、年齢、性別を調整した統合失調症患者86名と健常者86名のDCを比較しました。また、QT延長のある統合失調症患者とQT延長のない統合失調症患者とのDCを比較しました。抗精神病薬を服用している統合失調症患者の平均DCは健常対照者の平均DCと比較して有意に低く(統合失調症患者群3.89±2.6ms、健常対照者群7.51±1.74ms)、また、重回帰分析において、年齢(偏回帰係数(PRC)= -0.082)、抗精神病薬の使用(クロルプロマジン換算:100mgあたり、PRC= -0.12)がDCと負の相関を有意に認めました。個々の抗精神病薬について検討したところ、年齢(PRC= -0.099)とクロルプロマジン(100mgあたり、PRC= -1.99)、ゾテピン (66mgあたり、PRC= -0.36)、オランザピン(2.5mgあたり、PRC=-0.19)、クロザピン(50mgあたり、PRC=-0.69)がDCと負の相関を有意に認めました。一方で、DCとQT間隔との関連性は認めませんでした。
抗精神病薬の使用は、用量依存性にDCを減少させ、特にクロルプロマジン、ゾテピン、オランザピン、クロザピンなど受容体親和性プロファイルが多岐にわたる抗精神病薬において、DCを減少させやすいことが示唆されました。また、DCとQTcは独立した心臓死の予測因子である可能性が考えられ、これらの評価を組み合わせることで、抗精神病薬服薬中の統合失調症患者における心臓突然死の予測精度を向上させることができるかもしれません。
日本臨床精神神経薬理学会は、当講座において大変馴染みの深い学会です。これまでにもポール・ヤンセン賞や奨励賞など、当講座の先輩方が何人も受賞されておりました。尊敬する諸先輩方と同じ賞をいただくことができ、大変名誉なことと思っております。
今後も、当講座の、特に若手の先生たちが臨床研究の面で活躍してくれることを願っております。
最後に、本研究に協力していただいた獨協医科大学病院、不動ヶ丘病院のスタッフ、何より研究参加に御同意いただいた全ての患者さんに心より感謝申し上げます。
第20回日本うつ病学会総会で奨励賞を受賞して
獨協医科大学精神神経医学講座 徳満敬大
この度、第20回日本うつ病学会総会において、奨励賞を受賞しました。本研究は、日本精神神経科診療所協会と、日本臨床精神神経薬理学会のメンバーによる合同プロジェクト(MUSUBI)の成果のひとつです。この場を借りてお礼申し上げるとともに、内容について簡単にご紹介致します。
双極性障害は躁病エピソードと抑うつエピソードを繰り返す難治性の精神疾患です。再発を繰り返す度に、社会機能が低下することが知られているため、外来診療では症状再燃による入院を予防し、寛解を維持することが重要です。しかし、リアルワールドにおける双極性障害の入院予測因子は、不明な点が多いことが課題でした。私たちは、MUSUBIのデータを用いて、ベースラインの臨床的特徴と、その後1年間の入院発生の有無について多変量解析を行い、双極性障害患者の入院予測因子を検討しました。研究では、外来治療中の双極性障害患者について、ベースラインから1年間に入院が発生した割合は3.06%であることが明らかとなりました。次に、1年間の入院発生に関して多変量解析を行ったところ、ベースラインにおける低い全般的機能(GAF)スコア、双極I型障害、無職、物質使用障害の合併および躁病相が、統計的に有意な入院発生の予測因子であることが判明しました。特にベースラインにおけるGAFスコアは、低ければ低いほど、その後の入院リスクが高いことが明らかとなりました。私たちの研究によって、双極性障害外来患者さんの入院発生予測因子として、ベースラインのGAFスコアが重要であることが浮き彫りとなりました。一方で、今回明らかとなった予測因子が、それぞれGAFスコアに影響を与えることも知られています。
このため、物質使用障害および就労に焦点を当てた支援や、躁病エピソードの治療を意識した治療が、双極性障害患者の入院予防と寛解維持につながる可能性があると思われましたMUSUBI のデータ解析により、本邦における双極性障害患者さんの転帰に関する重要なリアルワールドエビデンスが得られました。この度は、貴重なデータの解析ならびに発表の機会を賜り、ありがとうございました。
第118回日本精神神経学会学術総会優秀発表賞を受賞して
獨協医科大学精神神経医学講座 菅原典夫
この度、「双極性障害外来患者における 3 年後治療反応の予測因子」と題して、第118回日本精神神経学会学術総会で発表したところ、優秀発表賞に選ばれました。本研究は、日本精神神経科診療所協会と、日本臨床精神神経薬理学会のメンバーによる合同プロジェクト(MUSUBI)の成果のひとつです。この場を借りてお礼申し上げるとともに、内容について簡単にご紹介致します。
双双極性障害は気分症状の増悪を繰り返し、長期の経過を有することが知られており、Real worldの経過に着目した研究が注目されています。そこで、2016 年の MUSUBI 1 次調査に参加した患者さん 3106 名について、その 3 年後に実施した 2 次調査までのデータを用いた治療アウトカム解析を実施しました。 2 次調査までの主要項目評価を完遂した対象者は 1,647 名でした。 3 年後の時点で19.3%の対象者が 1 年以上の持続的寛解を達成していた一方で、何らかの 47.5%が病相期にある状態でした。持続的寛解を予測する要因として、パーソナリティ障害を有していないことや、 1 次調査の時点で長い寛解状態にあることが分かりました。また、2 次調査で1 年間に抑うつ症状を体験していたことと関連する要因として、1 次調査時点における全般的機能 (GAF) が低いこと、希死念慮があること、寛解状態が短いことが明らかにされました。
MUSUBI のデータ解析により、我が国における双極性障害外来患者の自然史が明らかになるとともに、長期経過の予測因子が判明しました。この度は、貴重なデータを報告する機会を賜り、ありがとうございました。
第116回日本精神神経学会学術総会優秀演題賞を受賞して
獨協医科大学精神神経医学講座 徳満敬大
この度、「双極性障害患者に対する抗うつ薬の処方実態と患者プロフィール」と題して、第116回日本精神神経学会学術総会で発表したところ、優秀演題賞に選ばれました。本研究は、日本精神神経科診療所協会と、日本臨床精神神経薬理学会のメンバーによる合同プロジェクト(MUSUBI)の成果のひとつです。この場を借りてお礼申し上げるとともに、内容について簡単にご紹介致します。
双極性感情障害の治療に関して、抗うつ薬の処方については議論が分かれており、real worldの治療行動を調査した研究が注目されています。このため、MUSUBIの1次調査に参加した患者さん2075名のビッグデータを用いて、抗うつ薬の処方実態とプロフィールを解析しました。その結果、ベースラインでは、双極性障害患者さんの40.9%に抗うつ薬が処方されていることが明らかになりました。加えて、うつ病相にある患者さんは、他の病相に比べて、統計的有意に高い割合で抗うつ薬が処方されていました。抗うつ薬の種類は、デュロキセチンが最も処方されていました。また、抗うつ薬を処方されている患者さんは、統計的有意に機能の全体的評定尺度(GAF)が低値でした。さらに、抗うつ薬を処方されている患者さんは、気分安定薬の併用率が低く、抗不安薬および眠剤の併用率が高いことが分かりました。MUSUBIのデータ解析により、うつ病期のGAFが低い患者など、複雑な病像を呈する治療困難な症例に対して、寛解達成と社会適応水準の向上を目指し、ある程度選択的に抗うつ薬の処方が行われていることが判明しました。
多数の関係者の協力によって得られたこれらのビッグデータにより、日本の精神科医療の実態が明らかとなりました。この度は、貴重なデータを報告する機会を賜り、ありがとうございました。
第116回日本精神神経学会学術総会優秀演題賞を受賞して
獨協医科大学病院精神科神経科 レジデント 佐藤由英
このたび、日本精神神経学会で優秀発表賞を受賞いたしましたのでご報告させていただきます。電気けいれん療法Electro Convulsive Therapy (ECT)による発作後脳波の抑制を表す指標であるPostictal Suppression Index (PSI)は、良好なけいれん発作を得たことと関連するとされ、臨床的には機械評価だけではなく、目視によっても記録される指標です。今回は当科におけるうつ病患者51例でのECT結果を解析し、PSIと他の臨床指標や、治療予後との関連についての検討を行いました。その結果、PSIが抑制良好である場合、(1)ECT初回施行時のけいれん時間 (EEG endpoint)が長いこと、振幅 (Maximum Sustained Power)や対称性 (Maximum Sustained Coherence)が高いこと、交感神経系の興奮 (Peak Heart Rate)などと関連性を認めました。また(2)ECTコース終了の直近で評価された抑うつ症状の寛解率が高いことと関連する一方、ECT施行後から再入院までの生存曲線に差は認めらなかったことが分かりました。この受賞を励みに、今後も精神科の臨床や研究に精力的に取り組んで参りたいと思います。