支える周囲の方へ
摂食障害ってなんだろう?
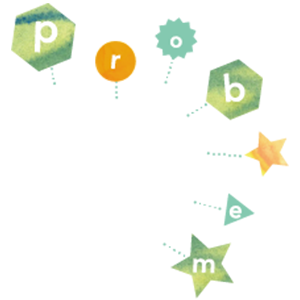
-
食べることを中心に色々な問題が現れる。
「急にやせたかも?」
そう感じたとき、そこには見えないつらさが隠れているのかもしれません。摂食障害は、食べ方の変化だけでなく、気分や、人との関わりの中にも、そっとあらわれることがあります。ときには、反発しているように見える言葉や態度に戸惑うこともあるかもしれません。けれどそれは、栄養のバランスが崩れて、じつは、心と体がつらいサインかもしれません。

-
体重や体型の感じ方に問題がある
まわりから見ると十分にやせていても、本人には「太っている」と感じられてしまうことがあります。その言葉に驚いたり、どう返せばいいのかわからなくなることもあるかもしれません。でもそれは、わがままや反抗ではなく、こころが苦しいときにあらわれるひとつのサインなのかもしれません。

-
長く続いてしまうことがある
少しよくなったかなと思っても、またつらそうな日が戻ってくることがあります。支えているつもりなのに、届いていないように感じたり、自分を責めたくなるような日もあるかもしれません。そんな日々が続く中で、本人も家族も、大変な時期だと思います。だからこそ、誰かにそっと話してみることも、大切なのかもしれません。
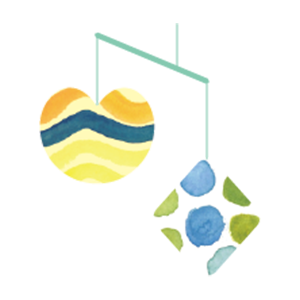
-
心と体の2つの症状がある
こころがつらいとき、体にも変化があらわれることがあります。食欲や眠り、疲れやすさやイライラなど、ことばにならないかたちで、あらわれることがあります。でも、それをすぐに「病気かも」と気づくのは むずかしいことです。だからこそ、「なんとなく気になる」という気持ちを、どうかそのままにせず、大切にしていてほしいと思います。

-
心と体への適切な治療と支援が必要
摂食障害の回復には、心と体の両方に向き合い、病院だけではなく、ご家族や学校、地域の支援機関とつながりながら、みんなで支えることが大切です。私たちは、限られた医療資源の中でも、地域の中で安心して相談できる場を少しずつ育てていきたいと思っています。どうかひとりで抱えすぎず、いっしょに考えていけたらと思っています。
摂食障害とは?
摂食障害とは、「食べること」に関する行動に問題が起き、それによって心と体の両方に不調があらわれる病気です。
単に「やせすぎている」だけではなく、体重や体型に対する強いこだわりや、不安・苦しさなどの気持ちも関係しています。
自然に治ることは少なく、長い間苦しんでいる人もいます。早く気づき、心と体の両方に適切な治療や支援を受けることが大切です。
摂食障害のタイプ
■ 神経性やせ症
無理にやせようと食事を極端に減らし、痩せていても「まだ太っている」と感じてしまいます。体重が増えることに強い恐怖を感じ、自分では問題に気づきにくいのが特徴です。重症になると命にかかわることもあります。
■ 神経性過食症
短時間で大量に食べたあと、「体重が増えるのがこわい」と思い、吐いたり下剤を使ったりして体重をコントロールしようとします。体には大きな負担がかかり、心のバランスも崩れやすくなります。
■ むちゃ食い症
むちゃ食いをするが、吐いたりせず体重が増えていきます。食べることが自分で止められず、罪悪感や自己嫌悪に苦しむ人が多くいます。
■ 回避・制限性食物摂取症
特定の食べ物への強い嫌悪感や不安のため、十分に食べられず、栄養が偏ったり、体重が増えにくくなったりします。やせたいという気持ちからではなく、食べ物そのものが怖い・気持ち悪いと感じるのが特徴です。
摂食障害は年齢や性別に関係なく起こります
摂食障害は若年女性に多い病気とされていますが、男性や大人でも発症することがあります。本人も周りの人も「まさか自分が…」と思いがちですが、誰にでも起こりうる問題です。
まずは話してみることから
「誰にも相談できない」「自分とは関係ない」と思っていませんか?
少しでも気になることがあれば、家族や先生、保健室の先生、相談窓口など、話しやすい相手に相談してみましょう。早めの気づきとサポートが、回復への大きな一歩になります。
- Q1,家ではどんなサポートができる?
- A. 無理に食べさせるのではなく、本人の気持ちに寄り添い、心配していることを伝えることが大切です。医療的なアドバイスや食事の管理は医師に任せ、本人の努力や変化を認めてあげましょう。
- Q2. 本人が病院に行きたがらないときは?
- A. 「治療で楽になれること」「夢や目標のために治療が必要であること」など、前向きな声かけを。以前に嫌な経験があった可能性もあるので、病院の体制を事前に確認するのもおすすめです。
- Q3. 職場や学校にはどう伝えたらいい?
- A. まずは「どんな病気か」を理解してもらうことが大切です。医師と連携して情報を共有し、「何に困っていて」「どう配慮してほしいか」を具体的に伝えましょう。たとえば「食事への配慮」や「外見への指摘を避ける」なども重要です。
- Q4. 本人に治す気がないのでは?
- A. 患者さん自身も「よくない」と感じていることが多いですが、不安や恐怖、感覚のまひなどにより自分をコントロールできなくなっているのです。決して“なりたくて”なっているわけではありません。
栃木県摂食障害支援拠点病院獨協医科大学精神神経科内
0282-87-2281受付時間:月曜日(祝日は除く) 9:00~15:00
栃木県摂食障害支援拠点病院では、
全例を直接治療するわけではありません。
受診希望の方には、地域や症状に応じて
適切と思われる医療機関をご案内します。